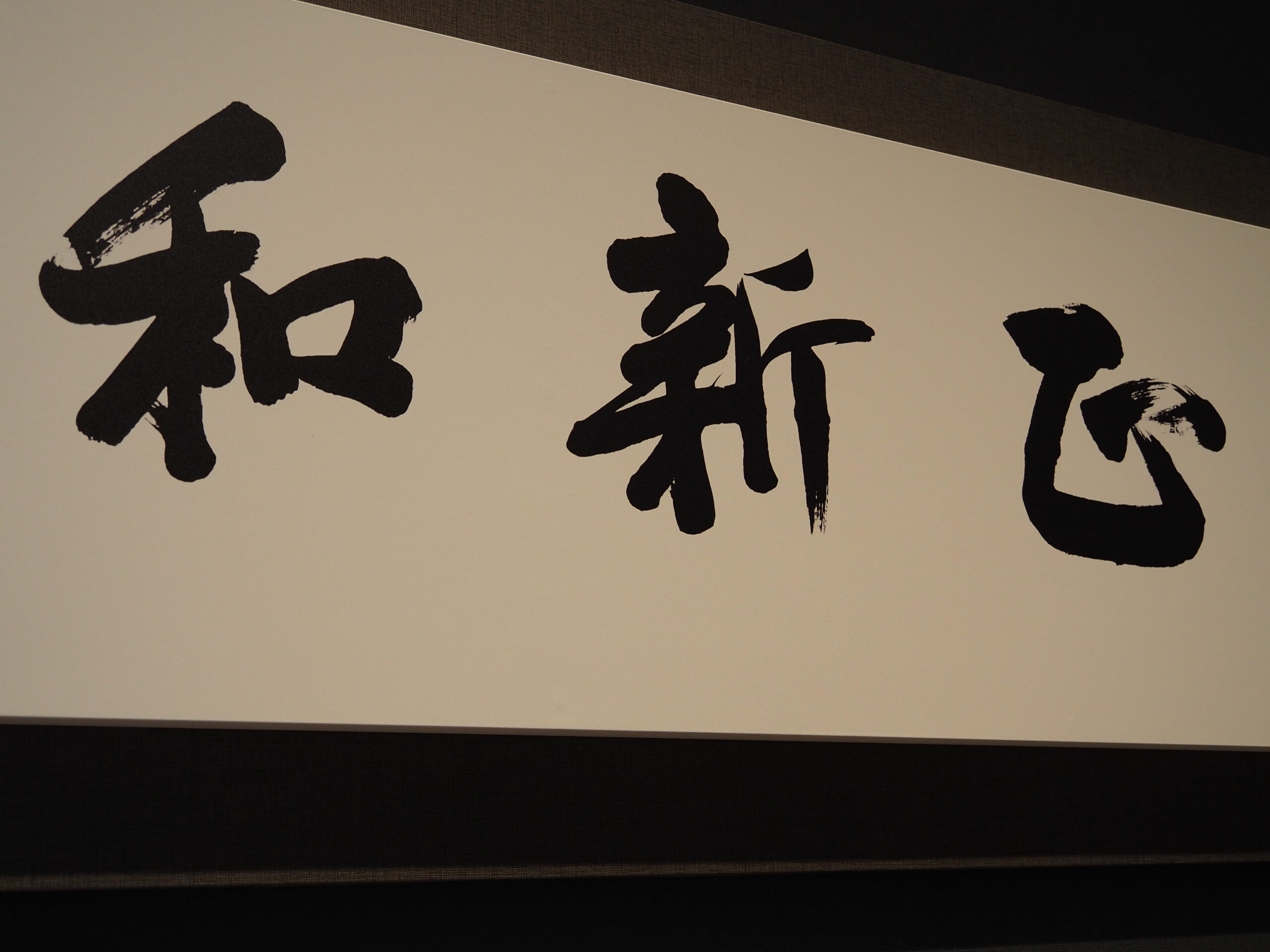孔子の言葉に学ぶ、勉強しない子どもへの処方箋
「うちの子、まったく勉強しなくて……」
塾や学校の面談で、あるいは家庭の夕食の席で、こんな悩みを抱えていらっしゃる保護者の方は少なくないでしょう。子どもが勉強に身を入れない姿を見ていると、不安にもなり、つい叱ってしまう。けれど、叱れば叱るほど子どもは心を閉ざし、ますます机から遠ざかっていく。
そんなとき、2500年以上前に生きた孔子の言葉が、今を生きる私たちにそっとヒントをくれます。
「学びて時にこれを習う、また説(よろこ)ばしからずや。」(論語・学而第一)
この言葉の意味は、「学んだことを、時に応じて復習し、実践する。これほど喜びに満ちたことはないではないか」というものです。
孔子は、学びを苦役とは捉えていません。学びとは、本来、人間の中にある「知りたい」「成長したい」「理解したい」という欲求を満たすものであり、心を豊かにする営みだと説いているのです。
子どもが勉強を嫌がるとき、もしかするとその「学ぶ喜び」を体験する機会をまだ得られていないのかもしれません。テストの点数、偏差値、内申点──そういった数字だけが「学びの成果」と思われがちな今、学ぶことそのものの“楽しさ”や“意味”が見えづらくなっているのです。
孔子は、こんなことも言っています。
「知る者は好き(この)ぶる者に如かず。好きぶる者は楽しむ者に如かず。」(論語・雍也第六)
つまり、「ただ知っているだけの人は、学ぶことを好きな人にはかなわない。そして、好きな人も、それを心から楽しんでいる人にはかなわない」ということ。
大人である私たちが「勉強は楽しい」と本気で思っているかどうか、それを子どもは敏感に感じ取ります。親が本を読み、学び、日々を豊かにしている姿を見せることで、子どももまた「学ぶことって悪くないかも」と思い始めるかもしれません。
「勉強しなさい」と言う代わりに、こんなふうに語りかけてみてはいかがでしょう。
「お母さん(お父さん)も最近、こんなことを知ったんだ。すごくおもしろかったよ。」
子どもは、親の言葉ではなく、親の“生き方”に影響を受けます。
勉強とは、試験のためにするものではなく、自分の人生を広げ、深めるための旅。孔子の時代も、今も、それは変わらない真理です。
学びの喜びを伝える第一歩は、まず親である私たちが、もう一度「学ぶことの意味」を見つめ直すことかもしれません。